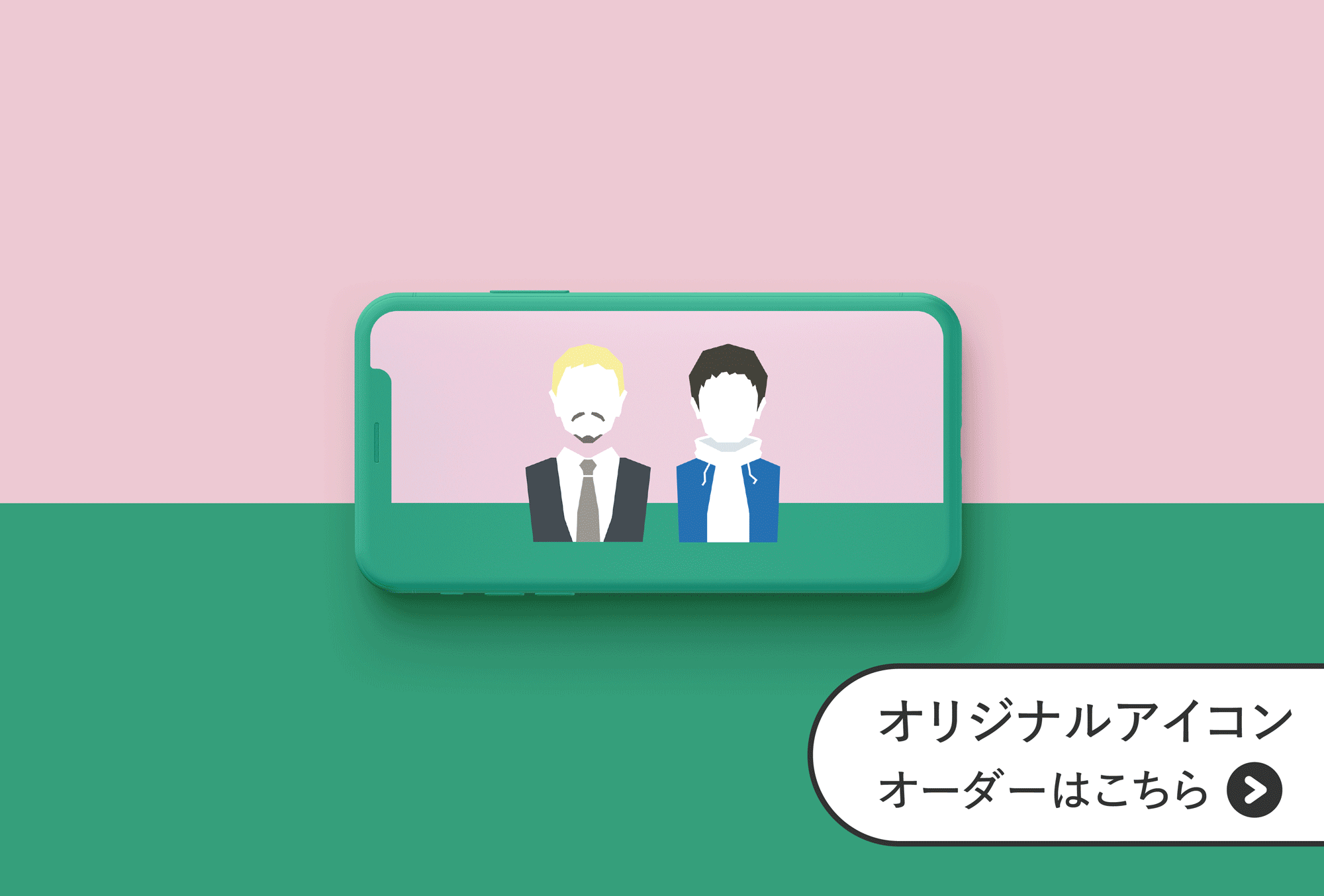デザインには形や色ばかりではなく、そこに社会と連動しながらおのずとにじみ出てくるものがある。
日本のグラフィックデザイナー、田中一光。
日本のみならず海外でも様々な賞を獲得し、企業の広告やオリンピック、万博などのデザインにも携わり、無印良品を生み出すなど幅広く活躍した日本を代表するデザイナーです。
今回はそんな田中一光の名言を紹介し、その言葉たちからの学びである「良くあることの大切さ」について考察しました。
田中一光とは?どんな人? 生い立ち・生涯・経歴を紹介
映画にハマった小学校時代
田中一光は1930年に奈良で生まれます。家は祖父の代から続くカマボコの製造業を営んでいました。両親は仕事に忙しく、一光は自由奔放に育てられたといいます。
小学校の時から映画が大好きだった一光は学校の近くにあった映画館に通いつめます。また似顔絵を描いて遊んだり、植物に興味をもち園芸を楽しむなど、様々なことに好奇心を持っていた子どもでした。
中学生時代は第二次世界大戦の渦中にあり、勉強よりも軍備を作るための機械工作をする学徒動員の毎日でした。一光が15歳の時の1945年に戦争は終わりました。
担任のすすめで美術学校に入学
家業のこともあり中学を卒業したら学業は終わりだと思いっていた一光ですが、担任であった絵画の先生から美術学校の進学をすすめられ京都市立美術専門学校の図案化に入学します。
デザインという言葉も確立されていない時代に商業美術である広告やポスターなどに触れます。また学校の演劇部に所属し、劇団活動にも熱中しました。
20歳で学校を卒業すると大阪の鐘紡に就職します。ポスターをつくりたかった一光ですが配属されたのはテキスタイルの部署でした。それでも鐘紡の宣伝部は関西でも有数のクリエイティブ組織で、一光はそこで多くの刺激を受けます。
大阪から東京へ
その後会社をクビになる挫折を味わいますが、鐘紡の人からの紹介で産経新聞に入社し、公文書を作る仕事をするかたわら、自主的なポスター制作に没頭します。
この取り組みが社長の目に留まると、一光は産経新聞が催すイベントのポスターなどを担当するようになっていきました。その後日宣美の会員になるなど、デザイナーとしての評価も得ていきます。
そして1957年に東京の広告デザイン会社であるライトパブリシティに入社しました。そこで多くの広告デザインを担当した一光は、1960年には日本のグラフィックデザインの第一人者でる亀倉雄策主導の日本デザインセンターの立ち上げに参加することとなります。
無印良品を生み出す
その3年後にはデザインセンターから独立し、自らの事務所を持った一光。西武などの大企業の商業デザインや大阪万博の幅広いクリエイティブに携わります。また数々の広告・デザイン賞を受賞するなど活躍を広げていきます。
そして1980年にはコピーライターである小池一子と共に無印良品を考案し、消費社会へのアンチテーゼとして新たな価値提案をデザインとコンセプトを通して世に提示しました。
デザイン界だけでなく日本の文化にも大きな影響を与えた田中一光は2002年、71歳の時に急性心不全でその生涯を静かに終えることとなります。
デザイナー田中一光の名言


デザインは異種交配していかないと次に発展しない。常に何と結びついたらいいのかを考えるのが大切なのである。例えば空間なのか、テクノロジーなのか、その異種交配の装置を作ることでデザインの領域が拡大していく。

多少の欠陥があってもいいものはいいという見極めは、何も審査員だけの問題ではなく、実際に制作する際にも大事なのである。

私のデザインの基本的な考え方は、企業とデザイナー、社会とデザイナーという双方向のチャンネルを常に確保しておくという点である。クライアントとの関係だけでデザインするだけでなく、消費者や観客の立場でデザインする。常にその三角形を意識しながらそれぞれを頻繁に往復することで、デザイン本来の姿に戻れると思っている。

グラフィックデザイナーのタイプに二つの性格があって、テーマに向かって出かけるタイプと、どんな主題でも自らの掌中に押さえ込んでしまうタイプとがあると思うが、私はどちらかというと前者で、自身の造形にそれほど固執しない。それぞれのプロ ジェクトに最善の回答を示すためには、自分以外の才能を進んで起用する。

常に社会的、企業的、芸術的な均衡を意識しながら、デザインを通じて時代そのものと対決せねばならない。

常に白紙の状態で素直に主題との接点を求め、私自身が現代人としての 「最良の生活者」になることが、トータルなデザインに対して何よりも必要なことではないかと思っている。

振り返ってみると、私は仕込みという作業に生きてきた。劇場も展覧会も、そしてパー ティもお茶会も、工夫して人をもてなし、サービスすることが好きなのである。
田中一光の名言を引用・参考にした文献
言葉から見た、田中一光てこんな人!
調和を大切にした人
戦後、敗戦国の日本は多くのものを失いました。生きるのも大変な中で青春時代を過ごした田中一光。そこから日本は高度経済成長により様々な大企業が生まれました。
田中一光のデザイナー人生はそんな日本の経済成長と一緒にありました。企業だけでなく、行政や国の催しなど幅広い仕事に携わってきた一光。
彼はデザイナーとしての過剰な自己表現ではなく、プロジェクトがうまくいくことを第一に考え、調和を大切にする人でした。
それは一光の「私は自身の造形にそれほど固執しない。それぞれのプロ ジェクトに最善の回答を示すためには、自分以外の才能を進んで起用する。」という言葉からも感じることができます。
ただのバランスを取るというのではなく、様々な個性や要素が組み合わさることで、自分の範疇を超えた発見や展開が生まれ、結果的に良いデザインとなる。
そんなデザイナーとしてのあり方が、今までなかった無印良品などのコンセプトを生み出したのだろうとも感じます。
調和を大切にした人。それが田中一光という人でした。
デザイナー田中一光の名言からの学び。[良くあることの大切さ]
他人にとっての良いを探す
今回の田中一光の名言で心に残ったのが、「常に白紙の状態で素直に主題との接点を求め、私自身が現代人としての 『最良の生活者』になることが、トータルなデザインに対して何よりも必要なことではないかと思っている。」という言葉でした。
デザイナーとはものを作るだけの単純な職業ではなく、アイデアや表現を決断し、世の中や人を観察、分析する仕事でもあります。
しかしそれはデザインだけの特別なことではありません。様々な仕事においてもアイデアは必要であるし、その仕事には人が関わっています。
「最良の生活者」
田中一光が表現したこの言葉は、一言で多くの意味を秘めていると感じます。
「やりたい仕事をやれ」「個性が大切だ」とよく叫ばれる昨今ですが、それはどこまでも他人ありきのことだと僕は思います。
他人を犠牲にしてまでやりたいことをやるのか。他人を犠牲にしてまで自分の個性を出すのか。自己犠牲が正しいとは思いませんが、やはり人間は1人では生きていけない以上、他人の存在は常に深く考えなければいけないことだと感じます。
最良とは自分ではなく他人にとって最良です。
他の人が生きやすく、暮らしやすい世の中を目指す。そんな思いやりの気持ちが新たなアイデアを生み出し、そして自分のやるべき仕事にも繋がっていくのかもしれないと、今回の田中一光の言葉に触れて感じさせられました。
他人にとっての良いを探す
日本を代表するグラフィックデザイナー、田中一光の名言からそれを学びました。